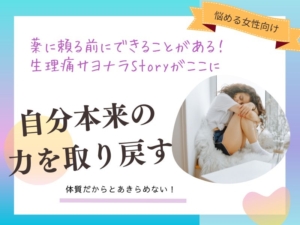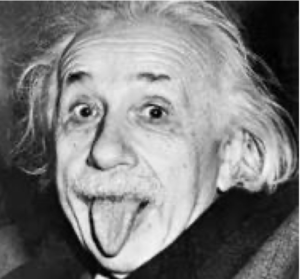多くの女性が日常生活の中で抱える悩みである「生理痛」や「PMS」について、先日 西洋医学または東洋医学(漢方)など、お薬を用いながら痛みや辛さを軽減していくという『対処療法』を含めた記事をご紹介しました。

今回は薬に依存するのではなく、生活改善等をおこなって症状を軽減させるための秘訣について書いていこうと思います。
札幌健康管理室では、代替療法を含め、自分自身がもつ本来の機能や働きを取り戻し、症状そのものを無くすという『根治療法』が重要だと考えております。この記事でご紹介する方法は、過去何十人もの生理痛を軽減または根治させ、室長自身も取り組んできたもので、効果は実証済みです。
これまで、生理痛やPMSで辛い思いをされてきた方ほど、「トンデモ療法だ」「月経ビジネスにはまりたくない」などの反発を覚えるかと思いますが、誤解を恐れずにいうと
「対処療法(ホルモン治療や薬物療法)には副作用がある、薬はリスク」
「症状を抑えるための治療で別の病気や症状がでてくることをあまり説明されていない」
という現状があります。
西洋医学や漢方治療を否定するものではありませんが、「薬に頼る前にできることがある」と常々思っています。
何かを無理やり押さえ込むやり方は、他の歪みを生みます。
生ゴミが臭うなら、消臭スプレーをかけるのではなくてゴミを捨てる、掃除をすることが大事ですよね?
体がウイルスや細菌を死滅させるためにリンパ活性スイッチをONにするため熱を出しているのに、薬で下げるのは本末転倒ですよね?
札幌健康管理室が推奨するのは、体が引き起こしていることには大切な意味があるということに気づくことと、カラダ本来の仕組みが損なわれているというお知らせ(サイン)が出ているときにそれを無視しないということです。
そのことについて、これからお伝えしていきたいと思います。
生理痛やPMSの症状に悩む女性の共通点
健康管理室の室長は10年間、看護学生に看護学を教えてきました。
母性看護学・小児看護学・地域看護学・在宅看護学・関係法規・看護理論や看護展開…etc
中でも一番力を入れてきたのは「母性看護学」です。
看護を学ぶ時、当たり前ですが病気について学びます。ですが、母性看護学は「正常の状態」を学ぶことが大切です。本来持っているカラダの仕組みについて学び、そこから逸脱した場合を見逃さずに対応するのです。
女性の体には、まさに「神仕組み✨」と言っても過言ではないほど、素晴らしいメカニズムがあります。
特に妊娠・出産(産後の回復)はそれを感じずにはいられません。そんなカラダ本来が持つ精巧な仕掛けの一つが「月経」という、命を繋ぐカラダの仕組みなのです。
生理痛が重い、動けないほどひどいという場合に、病気を含め「何かがおかしい」というカラダからのサインであることがほとんどです。
それは、
・今のライフスタイルに無理が祟って体を壊しかねないよ、修正して!
・カラダの緊張が強くて自律神経が乱れるほど疲弊してるから、休んで!
・カラダの力の前借り(持っている機能の浪費のようなもの)が多すぎて、後々困ることになるよ!
など、未病状態を告げる警告の場合が多いです。
母性看護の授業で月経について講義している時、授業終わりに生理痛がひどいと相談に来る女生徒に必ず次の質問をします。
「甘いものと乳製品、大好きじゃない?そして、冷え性でしょ??」
….答えは、そうですね、100%「Yes」です。
めちゃめちゃ体が冷えているのです。
→ 体を冷やさない工夫をしてオシャレできる?
→ 湯船にゆっくり浸かって血行よくしない?
→ ストレスで呼吸浅くなってないか、見直してみようよ?
崩れる女性ホルモンのバランス
動物性脂肪・乳製品など、脂肪の多い食生活は代表的な女性ホルモンである「エストロゲン」を過剰分泌させます。そもそも初経が始まるのは、体に脂肪が蓄えられ、その脂肪からエストロゲンが作られるからです。脂肪が溜まれば溜まるほど、エストロゲンが急上昇していきます。
また乳製品には生乳に含まれる性ホルモンや成長ホルモン(IGF-1)だけでなく、飼料と共に与えられる農薬などの化学物質(外因性環境エストロゲン)が含まれているため、乳製品をとりすぎる人はこれら「擬似エストロゲン(エストロゲンのような働きをする内分泌攪乱物質)」によりホルモンバランスが崩れます。
ちなみに、エストロゲンは骨抑制の性質があります。第二次性徴による初経が始まる前に身長が伸びて、そこから体に脂肪がつき始め月経が始まるのが本来の形とした場合、幼少期から脂肪たっぷりの食事で早くから体重が増加すると初経年齢が早まります。身長が伸びきる前に月経が始まると、エストロゲンの骨抑制の影響から、身長が低いままのことがあります。
1950年の平均初経年齢は15.2歳でしたが、2011年には12歳2.3ヶ月と3年早くなっています。
(早い子は小学3年生〜9歳くらいで初経を迎える子もいる)
また、エストロゲンには細胞増殖の働きがあるため、乳がんや子宮体がんなどの癌細胞増殖に関係してきます。
→ 乳製品を減らして、マグネシウムたっぷりの和食を増やせる?
→ 加工食品や食品添加物は体脂肪に「溜まる」よ?
→ ホルモンバランスの崩れを甘く見ると後で泣くかも?
砂糖中毒(シュガーホリック)
砂糖が体内に入ってくると血糖値が急上昇するため、それによって安らぎホルモンと呼ばれる「セロトニン」の血中レベルが上がり、気分が良くなります。しかし、そんな素敵な気分は長続きしません。
血糖値の急上昇が起きるとカラダは直ちに血糖を下げるホルモンである「インスリン」を分泌します。
血糖値急上昇⏩インスリンで即座に血糖値低下⏩血糖値下がりすぎる⏩甘いものが欲しくなる
の無限ループに陥りやすく、また幸せな気持ちや安らぎを感じたくなったら甘いもの!という、脳の思考回路も形成されてしまいます(ドーパミンという快楽物質がドバドバ出ます)
これで立派な砂糖中毒の完成です。
砂糖は体を冷やしますし、体に脂肪を蓄える一因でもありますから、その悪循環から抜け出すことが重要ですが、これが一筋縄ではいかないのです。
すぐに欲求を満たすことができるコンビニに陳列された限定商品や新製品がこれでもかと誘ってきますし、脳が「甘いものでストレスを発散せよ!」と命じ、強制的に従わせようとします。
味覚は2週間で修正できると言われているので、オススメは砂糖が欲しくなったら果物を少量食べる、甘いものが欲しくなったら温かいハーブティー等を飲むです。
その際、「ちょっとだけなら…」という問題を量に置き換えるのは厳禁です。
少量でもまた次が欲しくなるというのが、脳内でコカイン(麻薬)と同じ反応を示すと言われている砂糖の甘い罠なのですから。
→ スイーツの頻度減らせる?
→ 適量の果物に置き換えられる?
生理用ナプキンの実態とは
生理用ナプキンを選ぶ時、どんな基準で選んでいますか?
価格? 性能? かわいらしさ?
室長は産婦人科外来勤務経験があり、外陰部がナプキンの形に真っ赤にかぶれ、痛々しい姿を何度も目にしたことがあります。
産婦人科医は冷静に、「使っている(ナプキンの)メーカーは?」と問いかけ、当時は症状がひどい女性ほど決まって同じメーカーの名を答えていました。
生理用ナプキンのムレや痒み、ひどいただれがある時、あなたならどうしますか?
①軟膏を塗布して症状が良くなったら、とりあえず違うメーカーのものに変えて様子を見る
②ナプキンの種類をいろいろ変えて、肌に優しそうな、自分に合ったものを探す
③ナプキンについて学び、自分の選択肢を増やしてから自分に合った方法を取り入れる
これに対して、答えを出すための講座を札幌健康管理室では行っています。
生理痛やPMSとサヨナラするための講座です。
日本の初経教育はHow to のみ
SNSでは、「生理なんか、なくなればいいのに」「こんなに辛い思いを何年も続けて、もうたくさん!」といった、悲痛な声があふれています。
生理痛が重くなる原因を知らず、いえ、知ったとしても現在のライフスタイルを変えたくないと、根本原因に向き合うよりも、お手軽に解決できる方法はないかと、問題を未来へ先送りしがちです。
この記事を読んでいるあなたが今、「甘いものと乳製品を避けて、体を温める努力をして、生理痛がどう変化するか試してみない?」と言われたとしたら、どうでしょう?
「甘いものをやめられない…」
「チーズがない食生活なんて、無理」
「食べたいものを我慢したら、何でストレス解消すればいいの?」
という考えが浮かんできませんか?
こういうやりとりを繰り返し健康相談で聞いたきたからこそ思うのです。
初経教育で
・体を大切にすること
・月経を通して知るからの素晴らしい仕組み
・生理痛で悩まないために日常生活で何を気をつければいいのか
など、生理用ナプキンの当て方ではなく、女性が本来のカラダの仕組みを知って、その中で自分に合った方法を選択するという「考え方」を伝える大切さを。
学生に人気だった「月経の授業」
前述したように、長年看護学生に「月経の授業」をしてきました。
・体を大切にすること
・月経を通して知るからの素晴らしい仕組み
・生理痛で悩まないために日常生活で何を気をつければいいのか
をマインドマップを使いながら説明し、「利き酒」ならぬ「利きナプキン」のような実験をします。

学生たちは興味津々で、楽しみながら学びます。もちろん男子学生も。
そして必ず授業終わりに何人かの学生に囲まれます。
女子からは、「先生、私生理痛がひどいんです。試してよくなりたい!」
男子からは、「彼女の生理痛がひどいんです。この方法を教えたい!!」
そして、毎年3月に卒業生を送り出し、その夜の謝恩会で
「先生、私あれから生理痛なくなったんです!」
という、学生からのうれしいフィードバックまでがセットです。
「考え方を変えて行動を変える」
認知行動療法をご存知ですか?
前述したように、「やったほうがいいのはわかっていても、今の状態では取り組めない」「私の状況は変えられない」という考えから、現状維持を選択し続けてしまう方はとても多いです。
でも、本当に「現状維持」がベストとは思っていないはずです。
とてもできそうにないという気持ちや考えから、その結論に至っているだけだと思います。
諦めるしかない、無理に決まっているという状態を脱するために、「認知行動療法」について、まずは知知識として知ることから始めませんか?
認知行動療法(CBT)について、できるだけ簡単な言葉を使って説明します。
認知行動療法とは
① 心のメガネと心や考え方のクセ
私たちは、何か出来事があったとき、それぞれ違った「心のメガネ」を通して物事を見ています。
例えば、テストで間違えた問題があったとします。
ある人は「また間違えちゃった…僕はダメだ…」と落ち込むかもしれません。またある人は、「間違えたところを覚えれば、次はもっと良くなる!」と前向きに考えるかもしれません。
このように、同じ出来事でも心のメガネによって感じ方や考え方が変わります。
この心のメガネは心のクセとも言えます。人それぞれ心のクセや「こうである!」といった固定観念(考え方・自分にとっての常識)を持っていて、いつも同じように物事を見てしまうことがあります。
この心や考え方のクセが、私たちを困らせることがあります。
② 認知行動療法は何をするの?
認知行動療法は、この「心や考え方のクセ」に気づき、より良い見方や考え方に変えていく方法です。
例えるなら、心のメガネのレンズを磨いたり、新しいレンズに変えたりするようなものです。
③ 具体的にはどんなことをするの?
例えば、友達とケンカしてしまったとします。
- 出来事: 友達とケンカした。
- その時頭に浮かんだこと(考え): 「もう友達と仲良くできないかもしれない…」「きっと私のことが嫌いになったんだ…」
- その時感じた気持ち: 悲しい、不安、怖い
- その時とった行動: 部屋に閉じこもって誰とも話さない
この時、頭に浮かんだ考え(「もう友達と仲良くできないかもしれない…」)は、もしかしたら少し大げさかもしれません。
そこで、
- 「ケンカしたけど、前にも仲直りしたことがある」
- 「友達にちゃんと謝れば、また仲良くできるかもしれない」
というように、もっと現実的な考え方に変えてみます。
すると、気持ちも少し楽になり、友達に謝るという行動を起こせるかもしれません。
このように、
①何があったのか(出来事)
②その時どう考えたか(考え)
③どんな気持ちになったか(気持ち)
④どんな行動をとったか(行動)
を順番に見ていき、考え方を変えることで、気持ちや行動も変わっていくことを学び、実生活に活かしていきます。
辛い症状を和らげるために複数ある選択肢を学び、これまで絶対だと思い込んでいた自分の考えや信じていた常識を違う角度から見てみるなど、いつもと同じパターンを変えてみると違う結果が現れるかもしれません。
「常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションでしかない。」物理学者アルベルト・アインシュタイン
札幌健康管理室の「月経講座」では、これまで常識だと思っていた事柄に対するたくさんの「気づき」が生まれるような仕掛けをしています。もちろん、認知行動療法的な手法も取り入れながら講座を進めていきます。
ちなみに、札幌健康管理室では認知行動療法を用いたヘルスカウンセリングやコーチングを行なっております。
興味がある方は下記画像から詳細ページへお越しください。